ホン・ハクスンのクレイジーな世界
韓国出身のホン・ハクスンの作品は、僕が2014年から関わっている新千歳空港国際アニメーション映画祭の短編コンペの選考審査で最初知ることとなった。連載の第一回で、変態ナイトがマーケットや映画祭といった既存のチャンネルではなかなか評価しづらい作家を取り上げる新たなチャンネルであると話をしたが、ホン・ハクスンはまさにそこにぴったりの作家である。ピーター・ミラードやビックフォード、そしてエイミー・ロックハートといったこれまで紹介してきた変態ナイトの作家たちは、そうはいっても映画祭界隈で名前は知られている(ただ賞を獲らないだけ)。一方で、ホン・ハクスンをその界隈で認識している人はほとんどいないだろう。僕自身も彼の「ウィンク・ラビット」という作品を普通に選考から落としてしまった。ちょっと説明がつけづらいなと思って…

映画祭が彼の作品を選べない理由はよくわかる。彼の作品のルックが、子供向けに見えるからだ。「作家的なスタイル」に見えないからだ。子供向けのアニメーションは歴史的な流れをみても、そして作品自体の役割を考えても、表現・物語形式の革新性が求められるフォーマットではないので、映画祭的にもあまり嗅覚や見方があまり発達していないのが現状だろう。(エクスペリメンタルな子供向け作品という言葉がそもそも語義矛盾っぽい。)子供向け作品の多くはかなり固定・安定的なナラティブを用いるので、少しばかりそこから逸脱したものは「失敗」としてみなされてしまう可能性が高い。映画祭基準が生み出すその間隙みたいなものに、ホン・ハクスンの作品は吸い込まれていってしまうのだ。
ホン・ハクスンの作品は、たとえばこういう感じ。目に見えてエッジーな感じではないので、スッとスルーされてしまうような状況が起こりがちなのである。
ホン・ハクスン「全宇宙の友達の歌」
ただ、彼の作品は、そこで描かれているものが明らかにおかしいことを一旦認識してしまうと、ドツボにハマるようにして、観るたびに頭がおかしくなってしまうタイプのものである。彼の代表作「ウィンク・ラビット」を「変態ナイト」で初めてデビューさせたのは前述の新千歳空港国際アニメーション映画祭内のオールナイト枠で開催されたときだったけれども、深夜ゆえに観客の脳みそも良い感じに弱っていたこともあってか、会場の湧き方がとんでもなかったことを覚えている。アジア発の新たな変態スターの誕生を祝したい気分になった。
「ウィンク・ラビット」の狂った感じは実際に観てもらうのが一番理解してもらえるのだが、ウェブ上にアップされていないので作品を確かめたいと思うなら変態ナイトに来るしかない(良い宣伝!)。ただいちおう言葉で頑張って説明しておくと、基本的には、ウィンク・ラビットという名前のウサギ(その名のとおりウィンクをしまくる)が、友人たちと遊び回るだけ。ウィンク・ラビットはホン・ハクスンの様々な作品のなかに顔を出す、彼の代名詞的な存在である。
ウィンク・ラビットは、記号のようなものであるという。彼はウィンク・ラビット語を用いるが、彼自身が、ウィンク・ラビット語と同一平面上にいる存在である。何言ってるかわかりますかね? 言い方を変えると、ウィンク・ラビットは、実在しない。架空のキャラなんだから当たり前だろと思う人も多いだろうが、こういう説明ならどうか。「ウィンク・ラビット」には人間や鶏、牛、犬、タコなど様々なキャラクターが登場するが、ホン・ハクスン曰く、それらのキャラクターは実在するのだ。一方で、ウィンク・ラビットはそうではない。ウィンク・ラビットは図形動物なのである。図形や記号の延長線上にいる存在であり、そういう意味において、他のキャラクターとは違って、実在しない。(まだ納得しない? それもよくわかる。でも、あなたが納得のいかなさを感じる別の理由が最後の方に出てくるので、それまでもうちょっと待っていてほしい。)
ウィンク・ラビットが図形や記号、文字に近いという話は、「ウィンク・ラビット」という作品を観るときにその混乱を少しでも無くしてくれる手がかりになる(かもしれない)。ウィンク・ラビットは作品中で何度も何度も、ウィンクをしながら左右に往復運動する仕草を繰り返すのだが、その一連の動作が終わったときに、大きな「●」がウィンク・ラビットの右下に出るのだ。
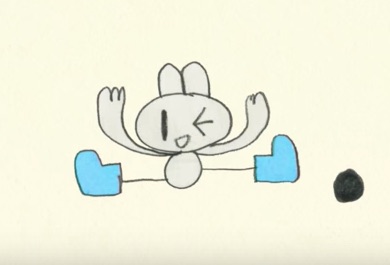
この穴みたいなものがなんなのか全然分からず、最初のうちはすごく怖くて、観るたびに背筋が凍る感覚があったのだが、今年の夏、ソウルに行った際に本人に会うことができて、謎が解決した。ホン・ハクスン曰く、この黒丸はピリオドなのだということだった。ウィンク・ラビットが記号だという話もそのときに聞いた。ウィンク・ラビットは記号だから、ひとつの動作が終わったということは、ひとつの文章が終わったということでもあり、だからピリオドが付く。すごくロジカル。
ホン・ハクスンが言うには、そもそもウィンク・ラビット自体が、たくさん丸を描いているなかからいつのまにか生まれたものなのだという。あくまで記号上の存在。彼が以前出した本が、その事実を証明してくれる。
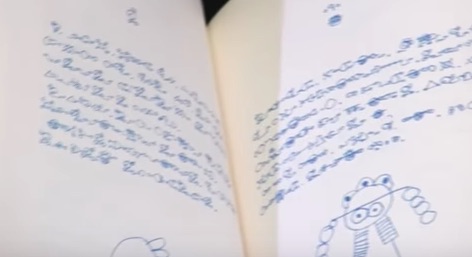
ちょっとわかりにくいかもしれないけど、ラビット語でこの本は全部書かれている。100ページ近く。当然読めない。だれか読める人がいるのかもわからない。これは完全に宇宙的な言語なのだ。ちなみにこういう文字自体には需要があるらしく、日本でも今年の夏に公開された映画「隠された時間」では、人気俳優カン・ドンウォン演じる神隠しにあっていた青年が書く秘密の言語として、このラビット語が採用されていたりする。幼馴染の女の子だけが読める言葉。つまり、そういう言語。
「ウィンク・ラビット」を観ていると気が狂いそうになるまだ別の理由として、こんなルックスなのに、妙にリアルに思えるというところがある。子供が描いたみたいな絵なんだけど、異様にヌルヌル動くし、平面ドローイングなんだけど、奥行き表現がすごかったり。なかでも一番ウワッとした気持ちにさせられるのが、ウィンク・ラビットが途中、友達の生物たちにわかめスープをふるまう場面があるんだけれども、配膳しすぎてお玉を持つ手がしびれる場面。あんな細かい生活描写はジブリでも観たことがなかったので、本当に驚いた。
そこにもやはり秘密があって、ホン・ハクスン曰く、この作品は「ドキュメンタリー」なのだという。ウィンク・ラビットはその誕生以来、彼の頭のなかにずっと住み続けていて、ことあるごとに自分を主役にした映画を作れという。ホン・ハクスンはその要望に応えるために、アニメーションを作るのだという。ただウィンク・ラビットはプロの俳優ではないし、その欲求もコロコロ変わるので、前述の「手がしびれる」みたいなNG的ショットが入り込んでしまう。だから、彼のアニメーション作品は、図形動物であるウィンク・ラビットが自分のなりたい役になってドラマを演じる様子を撮影するドキュメンタリー、ということになるわけだ。ホン・ハクスンは「キャラクター・ドキュメンタリー」というジャンルだと言っていた。これもすごくロジカルなんだけど、一方で意味がわからない。ただし、なんとなく、納得はさせられる。ちなみに、ウィンク・ラビットの動きがあまりにトリッキーなことがあり、そんなときは「そんな動き描けない!」と怒ったりすることもあるそうですし、ラビットがウィンクするのは、生まれ故郷の丸の世界の信号を受信するためだそうです。これらの話もなんとなく納得はする。でも心底ではない。
ホン・ハクスンがインディ・アニフェストのために作った映画祭予告編
次のページホン・ハクスンと「2歳」の知覚



