ほかでもない自分自身の「肉体」を描く
土居 お二人の作品には少女のキャラクターというのが中心にいるんですけれども、一方で多少の違いみたいなものもあると思うんです。片渕さんも少女のキャラクターについて、いろいろ(ローデンバック監督に)訊いてみたいという話をなさっていたと思うんですけれども……。
片渕 すごく簡単に省略された、抽象化された絵で描いてあるんですよね。でも、あの子が動いた時に、ああ、たしかにこういう人が存在しているんだなって、人格を感じる訳です。しかもそれを即興的にどんどん物語を描きながら自分の中で違う方向へ展開させつつも、その人格が揺るがないんですよね。どこに、何を芯として置いて、あの人物を作ったのかなと。それから、そもそもあの子には名前は無いのだろうか?ということも気になっていて。

ローデンバック
ご指摘いただいた通り、原作はほんの数ページしかないので、作品と原作はかなり違う。つまり原作の登場人物たちは、ある種の原型でしかない。本当の人物としての造形がなされているわけではない。人物のアイデアがそこにあるだけなんですね。
だから、私がこの作品を作るにあたって、とりわけ労力を割いたのは、原作にある原型でしかない登場人物を人格のある人間として作り上げ、同時にそれらの人物が普遍的な存在であるように注意を払ったんです。そのため、少女に名前をつけていません。
ただ一方で、少女は単なるアイコンではなく人間として生きるよう作業しました。この作品はもちろんアニメーションなので、少女の身体には心臓が無いんです。線と色があるだけなんですね。つまり、その肉体の動きを通して、生きる少女を作品の中に存在させたんです。
この作品の物語というのは要するに、少女がよりよい人生を目指して歩いていくというものです。私にとって非常に重要だったのは、少女の動き、少女がよりよい人生を目指して歩いていくその動きを、アニメーションとして作ることでした。
そしてこの作品は、少女が大人の女性になる物語です。つまり少女の身体がどう変化するか、それを描くことも非常に重要だったんです。またそれだけではなく、手という肉体の一部を切断されるため、そこをどう描くかもこの作品にとって非常に重要だった……もちろん原作にも少女の肉体というのはありますが、この作品においては、肉体を描くということを(原作よりも)大きく増幅させることができたと思います。
実は先週、この作品を日本の若い観客(中学生のクラスと高校生のクラス)に向けて上映していただく機会がありました。この作品を若い観客に見て頂くというのは、私にとって非常に重要なことだと思っていたので喜ばしい限りでした。
というのも、この作品で少女は「王女になるよりも少女でいたほうがいい」と語っているからなんです。どういうことかというと、他でもない自分自身の肉体を持つことを語っているからです。ところが、自分自身の肉体がどうあるべきかという主題は、多くの場合あまり語られてきておらず、普段誰もが語らないことなんです。それを語っている作品を、若い子どもたちに見せるということは、とても重要なことでした。
片渕 そうですよね。普通は「ケガレがない」といえば、いわゆるセクシュアルなことから隔離されていること(を呼ぶ)。しかしそのことに悪魔がおののくわけではない。そういうものも全部含めて「肉体」を持っている女の子だからこそ、悪魔はおののくんだという、その部分もすごく感銘を受けました。
現実そのものから、あえて離れる
ローデンバック ありがとうございます。こうしてお話しながら片渕さんの「この世界の片隅に」のことを想い出していたんですけれども、作品の中で日常の小さな身振り、家族生活での小さな身振りというものがきちんと描かれています。なかでも、日常の身ぶりを本当に細かく描いていらっしゃっていて。そういうことは、多くの作品が必ずしもやっていることではないと思います。
片渕 多分そうだと思うんです。作り手同士だと意外と「この世界~」と「手をなくした~」のビジュアル・表面上の違いよりも、ああ、おんなじことをやっているんだなって、こういう風にこの人は挑んでいったんだなって、解るところがすごくあるような気がするんですよね。一人の人物の人格を、どうやったら動きで表現出来るのか……さっきは「アイコン」と言いましたが、いわゆる偶像化したものではなく、魂というよりむしろ肉体とか日常性をもって、本当にそこにいるんだなって感じられるようなものにする、それを動きでもって作り上げていくという過程が何となく、ああ、こういうふうに挑んだんだなって、想像がつくような気がするんですね。ああ、自分たちも同じように、似ていたところが感じられたりとか、するわけですよね。
ローデンバック 確かにアニメーションでは、多くの場合、人物の動きや身ぶりで何かを表現するんですよね。つまりはデザインではない。おそらくこれはアメリカのアニメーション映画との大きな違いだと思うんですけれども、アメリカのアニメの場合、動きや身振りも勿論あるんですがそれ以前に、キャラクターのデザイン自体で既に何かを言ってしまうようなところがあると思います。ただ、私たちが作り上げたこの女性の主人公たちというのは、非常に少ない線で描かれていまして、静止画になってしまうとほとんど何も語られているものがない。しかし少女がいったん動き出してしまえば、そこで多くの事を語り始めるわけです。アニメーションというのは、本当に変な表現だと思うんですね。つまり、まったくの人工的なものです。そのアニメというものを通して非常に深い、人間性であったり現実(リアル)というものを描くんです。ただ、私たちふたりがやっていることというのは、現実をコピーするのではない。模写するのではなく、現実自体から離れて、いかに現実を再解釈してアニメとして描くか、つまり現実そのものから離れて描いているということ、それが私たち二人が大事にしていることだと思うんですね。大きな冒険、大きな物語というものを、一旦現実から離れることで私たちは描いていると思います。

少女、家族、観客たち
土居 もうすぐお時間になってしまうんですが、お二人にとても訊きたいことがあって……どちらも少女が主人公なんですけれども、同時に家族の物語でもあるじゃないですか。最終的に家族が再構成されていく。少女たちも新しい子と共に生きるんですが、それと同時に、その周りの家族もまた、新しいものを生み出していくという感じがある。お二人の作品はすごく勇敢に作られた作品だと思いました。それは観客をある種の「家族」にしてくれる。作品と一緒にみんなで一歩を踏み出していく、そんな共同体になれるような、そういったような感覚がすごくあったんですよね。ただ単に少女が成長していくだけじゃなくて、その周りの人たち、さらに言うと作品の周りにいる人たちもまた、何かしらその次の一歩を踏み出せるような、勇気の出る作品だなという共通点もあるのかなと思ったりもしています。
片渕 本当に一人の少女の魂の解放を描いているんだけれども解放されたときに、一人ぼっちではない。娘でありながら、さらに子供に恵まれていたり、男性とパートナーとしての関係を得ていく。やっぱり彼女自身が、周りの人に恵まれていくことによって、その人が本当の意味で解放されたんだろうなということが判る感じがするんです。ひとりぼっちで生きていくというだけではなくて、彼女は自分自身の家族を作り上げていく、そういう力も得ていったんだなあと、そういう感じもすごくしましたね。
ローデンバック まさに仰っていただいたことで、ラストシーンについては、プロデューサーと一種のケンカ……大論争になってしまいました。王子と再会したとき、少女はもう王子を必要としていないわけだから、王子を捨てて一人で旅立つべきだ、というのがプロデューサーの意見だったんです。それに、プロデューサーにとっては、王子は本当にダメな奴で、必要がないという考えだったんですね。私にとってはこの点は非常に重要でした……確かにプロデューサーの言っている事には一理ありまして、つまり少女は王子なしでも生きていけるし、手が無くても一人で生きていけるんです。ただ、自由であるということは、一人であるということがその自由を保障しているわけではないのです。それに、確かに王子無しで生きていくという選択肢もあると思います……少女は彼を必ずしも必要としていないかもしれません。ただ、彼女は王子がいてくれることを望む選択肢もあるわけです。それに、100%素晴らしい人間でなければ、その相手を欲しない・必要としない……そういうわけでもない。
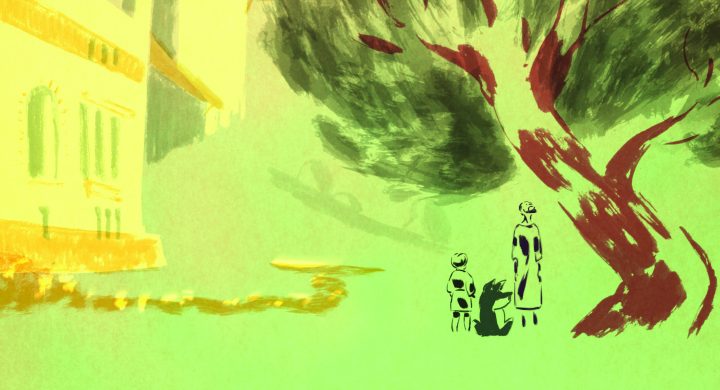
片渕 だから、一番最後に娘と子どもが二羽の鳥になって、あぁ、二羽なのかな、王子は自分の城を捨てて一緒に鳥になって飛んでいけるのだろうかと思ったら、ちゃんと羽ばたいていける、それがものすごく大きな救いになって、いいんですよね。
ローデンバック そうですね。王子はちょっと飛び立つまで時間がかかっちゃうんですけれども、それでも最終的には飛べるんです。さっき、王子はダメな奴だと言いましたが、本当はダメじゃないんです。単にちょっと、色々物事を理解するのに時間がかかってしまう人なんです。それに、男の子ってのは、だいたいそういうものです。
土居 うまく結論が出たところで(笑)今日のトークを終わりにしたいと思います。




